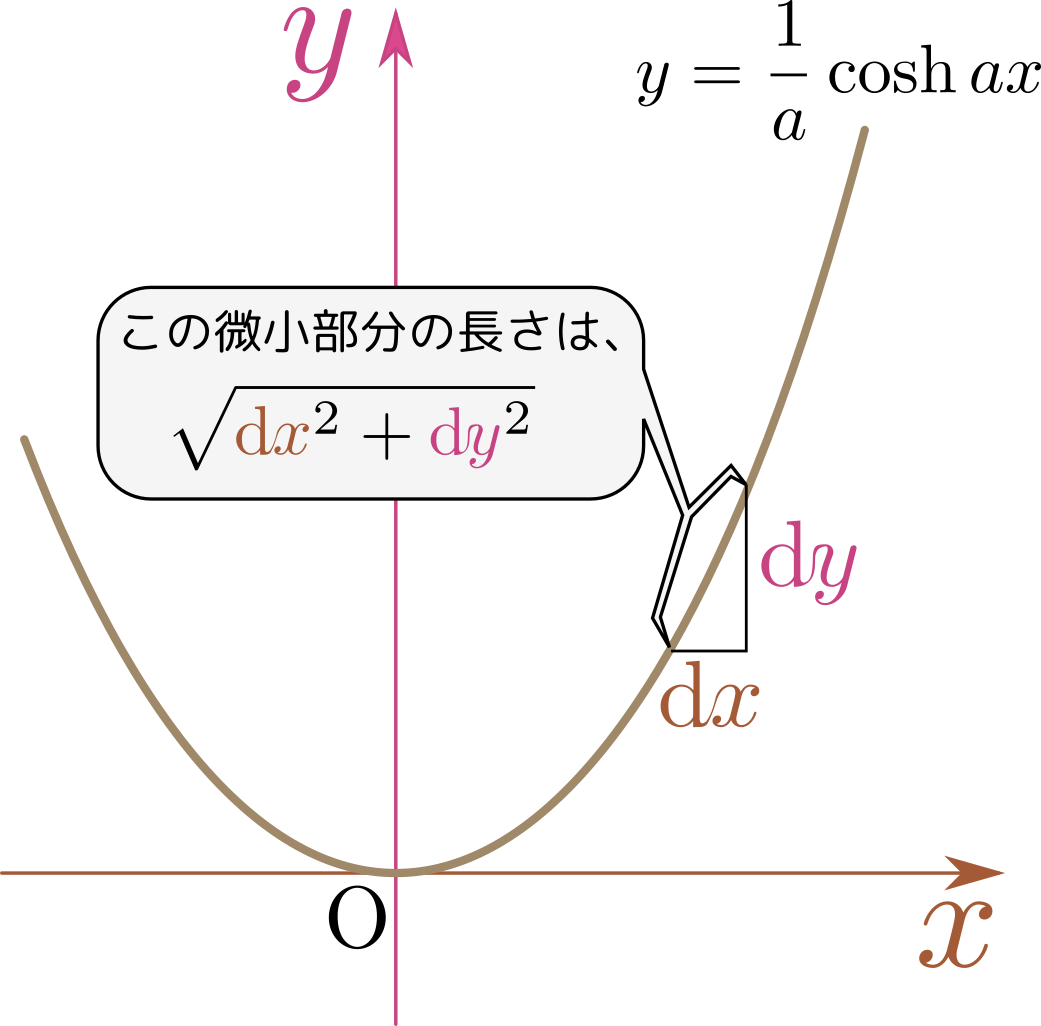自然科学のための数学IIの期末試験
- 必須問題の全てと、選択問題から2問を選んで答えること。選択問題は1問15点である。3問以上答えた場合は点数の高いものから2問の点数を採用する。
- 途中経過も書くこと。答だけ書いてあって間違っていたら0点だが、途中経過が書いてあれば部分点が得られる。また、答だけが合っていてもどこから出てきた答なのか経過不明であれば減点することもある。
- この試験の点数
- この試験の点数$\times 0.7+$授業中小テストの平均点$\times 0.3$
必須問題1
- (1) 微分方程式${\mathrm d^2 f(x)\over \mathrm dx^2}=x$の一般解は$f(x)={1\over 6}x^3+C$($C$は任意の定数)である。
- (2) ${\mathrm d y\over \mathrm d x}+5xy=x^3$という微分方程式は線形微分方程式だから、$y=f(x)$と$y=g(x)$という解があれば、$y=\alpha f(x)+\beta g(x)$($\alpha,\beta$は定数)も解である。
- (3) ${\partial U(x,y)\over \partial x}=y,{\partial U(x,y)\over \partial y}=x$である場合、${\partial U(x,y)\over \partial x}=y$を積分することで解の一つは$U(x,y)=xy$とわかる。同様に${\partial U(x,y)\over \partial y}=x$を積分して$U(x,y)=xy$を得るから、この二つを足すことで$U(x,y)=2xy$が解だとわかる。
←解答を見たい人はこの三角をクリック
(1)の答は「二階微分方程式の一般解は2個のパラメータを含まなくてはいけないから×」でよい(この事実をちゃんと認識しているかどうかを問いたい問題だった)。実際に解いてみせて本当の一般解$f(x)={1\over6}x^3+Bx+C$を出して「$Bx$が必要」という説明も、もちろんOK。
(2)は重ね合わせの原理が適用できるのは「線形斉次微分方程式」の場合であるという点がわかっていれば「非斉次なので×」という答が出たはず。
この方程式は「線形非斉次方程式」なので、「非線形だから×」のような解答は減点した。
(3)はもちろん$U(x,y)=xy$が正しく、二つの積分を足す必要はまったくない。よって「足すのは間違いだから×」や「$U(x,y)=2xy$では${\partial U(x,y)\over\partial x}=y$にならないから×」などと答えて欲しい。
以上三つは授業中で「こんな間違いしちゃダメよ」と説明した部分をそのまま出したが、○○○と答えている人もいた。
必須問題2
- (1) $\left({\mathrm d \over \mathrm dx}-5\right)y=0$
- (2) $\left(\left({\mathrm d \over \mathrm dx}\right)^2-8{\mathrm d \over \mathrm dx}+16\right)y=0$
- (3) ${y\over x}\mathrm dx+\log x \mathrm dy=0$
- (4) $2y\mathrm dx+x\mathrm dy=0$
- (5) ${\mathrm d y\over \mathrm d x}+y=\mathrm e^x$ (積分定数などは自分で適当に置いてよい)
←解答を見たい人はこの三角をクリック
(1)は変数分離してもいいし、「微分して元の5倍になる(${\mathrm d \over \mathrm dx}y=5y$)から$y=C\mathrm e^{5x}$」のように答えてもよい。
$y=\mathrm e^{5x}$のように未定パラメータを忘れたり、なぜか$y=\mathrm e^{5x}+C$のように足し算で積分定数をつけている誤答があった。
(2)は$y=\mathrm e^{\lambda x}$と置いて特性方程式を作ると$(\lambda-4)^2=0$となって重解となる場合。よって、$y=(Ax+B)\mathrm e^{4x}$が答え。
$Ax\mathrm e^{4x}$の方の解を忘れている誤答が頻出。「二階微分方程式の一般解は2個のパラメータを含むはず」という感覚を持つことは大事。
(3)は全微分形になっていて$\mathrm d(y\log x)=0$と直せるから、$y\log x=C$で$y={C\over\log x}$となる。あるいは変数分離で${\mathrm dy\over y}=-{\mathrm dx \over x\log x}$とする。右辺の積分が難しいと思うかもしれないが、${{1\over x}\over \log x}\mathrm dx={(\log x)'\over \log x}\mathrm dx$と考えれば積分結果は$\log y= -\log(\log x)+C$となる。これを変形して$y={D\over \log x}$。
全微分形であることに気づかず苦戦している人が多かったが、変数分離でも積分をちゃんと行えば解ける。
(4)は積分因子として$x$を掛ければ全微分形になり、$\mathrm d(x^2y)=0$と直せるから、$y={C\over x^2}$。あるいは変数分離して${\mathrm dy\over y}=-2{\mathrm dx\over x}$として、$\log y=-2\log x+C$。これを変形して$y={D\over x^2}$。
最後で変形を間違えて$y={1\over x^2}+D$と足し算にしてしまった人が頻出したが、対数で足し算は$\log$を外すと掛算になる。
(5)は、非斉次方程式だからまず斉次にすると${\mathrm d y\over \mathrm d x}+y=0$で、この解は$y=C\mathrm e^{-x}$。ここで、
【解き方1】 右辺が$\mathrm e^x$だから、特解もこれに比例するだろうと考えて$y=A\mathrm e^x$と置いて左辺に代入すると、$2A\mathrm e^x$となるから、$A={1\over2}$なら解。よって特解は${1\over2}\mathrm e^x$、と考える。一般解はこれに$C\mathrm e^{-x}$を足す。
【解き方2】 定数変化法を使って、$y=C(x)\mathrm e^{-x}$と置く。代入すると $$ \begin{array}{rl} {\mathrm d\over\mathrm dx}\left(C(x)\mathrm e^{-x}\right)+C(x)\mathrm e^{-x}=&\mathrm e^x\\ {\mathrm d C(x)\over\mathrm dx}\mathrm e^{-x}=&\mathrm e^x\\ {\mathrm d C(x)\over\mathrm dx}=&\mathrm e^{2x}\\ C(x)=&{1\over 2}\mathrm e^{2x}+D~(Dは積分定数)\\ \end{array} $$ と計算する。答は${1\over 2}\mathrm e^{x} + D\mathrm e^{-x}$。
必須問題3
- この生物は体表面から栄養を取り込むので、生物の成長速度は表面積$S=4\pi r^2$に比例するだろう。
- この生物は自分の身体を維持するために、体重に比例したエネルギーを必要とするだろう。そのエネルギーは体積$V={4\pi r^3\over 3}$に比例する。
- (1) この生物の体積変化を表す微分方程式を立てよ。
- (2) この生物の成長が止まっている。その時の$r$はいくらか。
- (3) $k\neq0$の場合の微分方程式を解け(ヒント:(2)の答が特解になる)。
- (4) $k=0$だったら微分方程式の解はどうなるか。
←解答を見たい人はこの三角をクリック
(1) ${\mathrm dV\over\mathrm dt}=KS-kV$。あるいは$S=4\pi r^2,V={4\pi\over3}r^3$を代入して、 $$ \begin{array}{rl} {\mathrm d\left({4\pi\over3}r^3\right)\over\mathrm dt}=&K\times 4\pi r^2 - k\times {4\pi\over3}r^3\\ 4\pi r^2 {\mathrm dr\over\mathrm dt}=&K\times 4\pi r^2 - k\times {4\pi\over3}r^3\\ {\mathrm dr\over\mathrm dt}=&K - {k\over3}r \end{array} $$ のように計算したものも可。
問題文に書いてある通りの情報を式にしてい${\mathrm dV\over\mathrm dt}=KS-kV$を答えてくれればよかったのだが、何やら意味のわからない計算をして、$K{\mathrm dS\over \mathrm dt}-k{\mathrm dV\over \mathrm dt}$などと答えていた人がいた。
(2) (1)の答えの右辺が0になるときだから、$r={3K\over k}$。
「止まっている」に半径が減っている状況を加えて$r<{3K\over k}$と不等式にしている人もいた。
(3) 解くべき微分方程式は、${\mathrm dr\over\mathrm dt}=K - {k\over3}r$。これは$r={3K\over k}$という特解を持つ。斉次にした${\mathrm dr\over\mathrm dt}=- {k\over3}r$の解は$r=A\mathrm e^{-{k\over3}t}$であるから、特解を足して$r=A\mathrm e^{-{k\over3}t}+{3K\over k}$が解。
${\mathrm dV\over\mathrm dt}=KS-kV$に$V={4\pi r^3\over 3}$を代入した $$ {\mathrm d\left({4\pi\over3}r^3\right)\over\mathrm dt}=K\times 4\pi r^2 - k\times {4\pi\over3}r^3 $$ で、微分を実行せずいきなり$4\pi r^2$で割って $$ {\mathrm d r\over\mathrm dt}=K- {k\over3}r $$ としている答案があったが、もちろんそんなことはできない。微分をちゃんと実行してから割り算しないと。
${\mathrm dV\over\mathrm dt}=KS-kV$からいきなり「斉次にして」と言って${\mathrm dV\over\mathrm dt}=-kV$としている人もいたが、この項$KS$は今考えている変数である$r$を含んだ式なのだから、そんなことはできない。同様に、$S$を勝手に定数だと思い込んで微分方程式を解いている人が多数いたが、何が変数で何が定数かはちゃんと把握して考えないと。
(4) $k=0$の場合の微分方程式は${\mathrm dV\over\mathrm dt}=KS$で、 $$ {\mathrm dr\over\mathrm dt}=K $$ となるから、 $$ r= Kt+C $$ が解。
必須問題4
- (1) $r$を$x,y$で表したのち、$y$を一定にして$x$で偏微分したもの$\left({\partial r\over \partial x}\right)$を求めよ。
- (2) $x=r\cos\theta$を$\theta$を一定として$r$で偏微分したもの$\left({\partial x\over \partial r}\right)$を求めよ。
- (3) 上で求めた二つの掛算、${\partial r\over \partial x}\times{\partial x\over \partial r}$は1にならないが、${\partial r\over \partial x}\times{\partial x\over \partial r}+{\partial r\over \partial y}\times{\partial y\over \partial r}$なら1になることを確認せよ。
←解答を見たい人はこの三角をクリック
(1) $r=\sqrt{x^2+y^2}$なので、${\partial r\over \partial x}={x\over\sqrt{x^2+y^2}}$。
(2) ${\partial x\over \partial r}=\cos\theta$。
(3) ${\partial r\over \partial x}\times{\partial x\over \partial r}={x\cos\theta\over\sqrt{x^2+y^2}}=\cos^2\theta$で1ではない。同様の計算を行なうと${\partial r\over \partial y}\times{\partial y\over \partial r}=\sin^2\theta$なので、二つの和を取ると1になる。
選択問題A
- (1) 微分方程式 $ {\mathrm d ^2\over \mathrm dx^2}f(x)=f(x)+2 $ の一般解を求めよ。ただし、${\mathrm d ^2\over \mathrm dx^2}f(x)=f(x)$の解が$f(x)=A\mathrm e^x+B\mathrm e^{-x}$($A$と$B$は定数)であることを使ってよい。
- (2) 同様に、微分方程式${\mathrm d ^2\over \mathrm dx^2}f(x)=f(x)+x$の一般解を求めよ。
←解答を見たい人はこの三角をクリック
- (1)斉次にした方程式の一般解は問題文に与えてあるので、非斉次の特解を求めて足せばよい。$f(x)=-2$が特解になるから、$f(x)=A\mathrm e^x+B\mathrm e^{-x}-2$。
- (2)同様に、$f(x)=A\mathrm e^x+B\mathrm e^{-x}-x$。
選択問題B
- (1) 長径$a$、短形$b$の楕円の面積は$S=\pi ab$である。互いに依存する三つの変数$S,a,b$について、「$b$を一定として$S$を$a$で偏微分」、「$S$を一定として$a$を$b$で偏微分」、「$a$を一定として$b$を$S$で偏微分」の三つの計算をして、積${\partial S\over \partial a}\times{\partial a\over \partial b}\times{\partial b\over \partial S}$を計算せよ。
- (2) 半径$r$、高さ$h$の円柱の体積$V=\pi r^2 h$の3変数$r,h,V$に関して、上の(1)と同様の計算を行え。
←解答を見たい人はこの三角をクリック
- (1) $S=\pi ab,a={S\over \pi b},b={S\over pi a}$と式を作って、 $$ \begin{array}{rl} {\partial S\over \partial a}=&\pi b\\ {\partial a\over \partial b}=&-{S\over \pi b^2}\\ {\partial b\over \partial S}=&{1\over \pi a}\\ {\partial S\over \partial a}\times{\partial a\over \partial b}\times{\partial b\over \partial S}=&\pi b\times\left(-{S\over \pi b^2}\right)\times{1\over \pi a}={S\over \pi ab}=-1 \end{array} $$ となる。
- (2) $V=\pi r^2h,r=\sqrt{V\over \pi h},h={V\over \pi r^2}$と式を作って、 $$ \begin{array}{rl} {\partial V\over \partial r}=&2\pi r\\ {\partial r\over \partial h}=&{1\over2}\sqrt{V\over \pi h^3}\\ {\partial h\over \partial V}=&-{1\over \pi r^2}\\ {\partial V\over \partial r}\times {\partial r\over \partial h}\times{\partial h\over \partial V}=&2\pi r\times {1\over2}\sqrt{V\over \pi h^3}\times \left(-{1\over \pi r^2}\right)=-1\\ \end{array} $$ となる。
最後の$=-1$まで計算して欲しかったところだが、そこまでやってなくても点は与えている。
こちらも最後の$=-1$まで計算して欲しかったところだが、そこまでやってなくても点は与えている。
これは授業で「$-1$になる」ということを強調したので、実際に計算するときもそれがヒントになったはず。しかし、$-1$になってない解も多かった。
選択問題C
←解答を見たい人はこの三角をクリック
式を整理すると、 $$ \mathrm d m w +m\mathrm d v=-mg \mathrm d t $$ ここで$\mathrm dt=-{\mathrm dm\over M}$を使って$t$を消去すると、 $$ \mathrm d m w +m\mathrm d v=-{mg\over M} \mathrm d m $$ 変数分離して、 $$ \mathrm dv = -w{\mathrm dm\over m} -{g\over M} \mathrm d m $$ となり、積分の結果 $$ v=-w\log m -{mg\over M}+C $$ $m=m_0$のときに$v=0$という初期条件ならば $$ v=w\log\left({m_0\over m}\right)+{(m_0-m)g\over M} $$ となる。$\mathrm d m = -M\mathrm d t$として$\mathrm dm$を消している人がいたが、その場合は変数である$m$を$t$で表さなくてはいけない。それをやらずにまるで$m$を定数のように扱っている間違いが多かった。
選択問題D
- (1) $f(1)=0$を示せ。
- (2) この関数は$f'(x)={f'(1)\over x}$を満たすことを示せ。
- (3) $f'(1)=a$($a$は定数)とすると、$f'(x)={a\over x}$である。この微分方程式を解いて、$f(x)$を求めよ。
←解答を見たい人はこの三角をクリック
(1) $y=1$を代入すれば、$f(x)=f(x)+f(1)$となるから、$f(1)=0$。
なぜか$x=0$を代入している人がいたが、問題文に「$x>0$で定義された関数」と書いてあるのだからそれはダメ。
(2) 両辺を$y$で微分すると、$f(xy)$の微分は$xf'(xy)$になり、右辺の$f(x)$は微分すると消えるから、$xf'(xy)=f'(y)$。微分が終わったあとで、$y=1$と置くと、$xf'(x)=f'(1)$。
$f'(x)={a\over x}$を積分して、$f(x)=a\log x +C$($C$は積分定数)。しかし$f(1)=0$にならなくてはいけないから、$C=0$。よって、$f(x)=a\log x$。
積分定数$C$を残してしまっている人がいたが、(1)で考えた条件があるのだから積分定数は決まってしまう。
選択問題E
- (1) $f(x,y)=x+by$($b$は定数)と仮定して、これが解になるように$b$を求めよ。その解を使うと、一般解はどのように書けるか。
- (2) 変数分離形$f(x,y)=X(x)Y(y)$を仮定して解け。
←解答を見たい人はこの三角をクリック
(1) $\left(2{\partial\over \partial x}+{\partial\over \partial y}\right)\left(x+by\right)=2+b$となるから、$b=-2$とすればよい。つまり、$f(x,y)=x-2y$が一つの解。実は$x-2y$の関数であればなんでも解だから、$g(x)$を任意の微分可能な関数として、$g(x-2y)$が解。
(2) $\left(2{\partial\over \partial x}+{\partial\over \partial y}\right)X(x)Y(y)$を計算すると、 $$ \begin{array}{rl} 2{\mathrm d^2 X(x)\over\mathrm dx^2}Y(y)=&-X(x){\mathrm d^2 Y(y)\over \mathrm dy^2}\\ 2{{\mathrm d^2 X(x)\over\mathrm dx^2}\over X(x)}=&-{{\mathrm d^2 Y(y)\over \mathrm dy^2}\over Y(y)}\\ \end{array} $$ となる。両辺が定数$\alpha$だと仮定し、$X(x)=\mathrm e^{{\alpha\over2}x},Y(y)=\mathrm e^{-\alpha y}$が解であるから、$\mathrm e^{{\alpha\over2}(x-2y)}$が一つの解(一般解は、さまざまな$\alpha$の値の解の線形結合)。
選択問題F