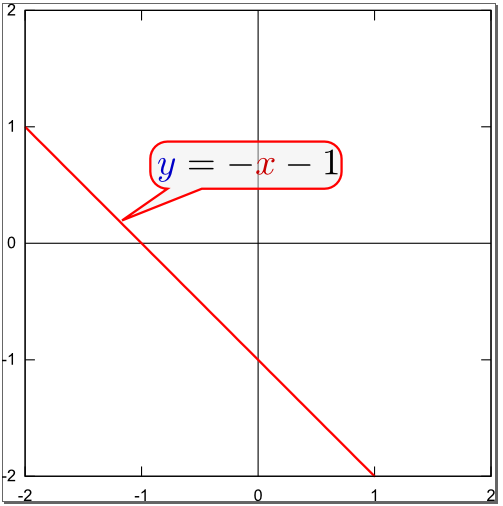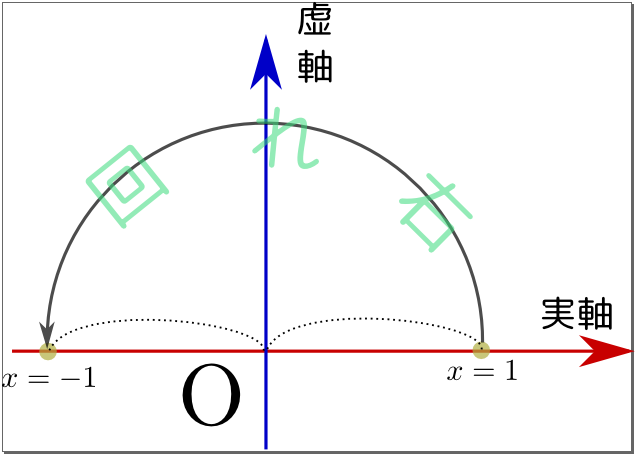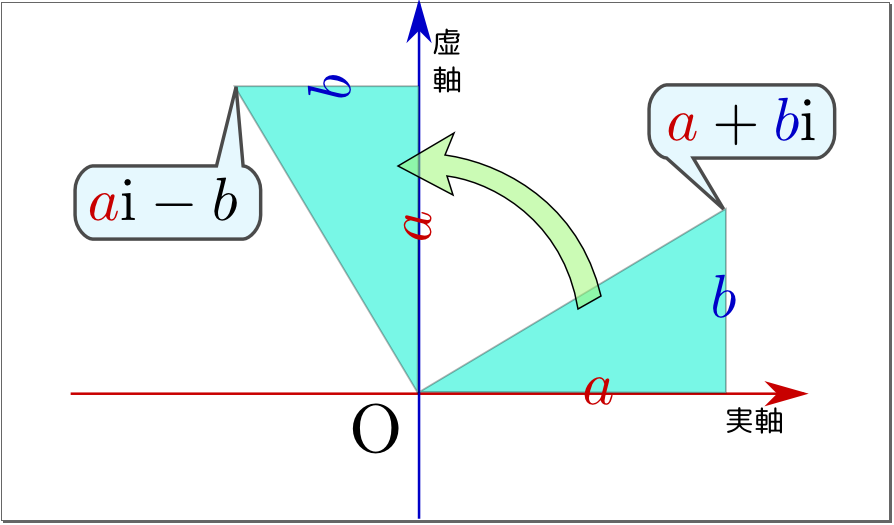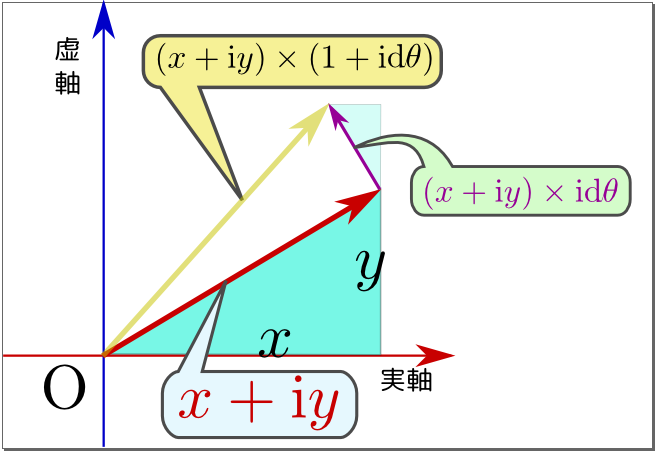一般的な線型微分方程式の解き方を考える前に、まずは簡単な例を考えよう。
というわけでここでは線型斉次で、かつ係数$A_i({x})$が定数$A_i$である場合、すなわち
\begin{equation}
\left(
A_n\left({\mathrm d\over \mathrm dx}\right)^n
+A_{n-1}\left({\mathrm d\over \mathrm dx}\right)^{n-1}
+\cdots
+A_{1}{{\mathrm d\over \mathrm dx}}
+A_0
\right){y} =0\label{teisuusenkeiseiji}
\end{equation}
を解く一般的な方法を示そう。
特性方程式
まず、この微分方程式には、${\mathrm e}^{\lambda {x}}$という形で表せる解がある($\lambda$はこの後決める定数である)。これが解になるかどうかを確認するために代入してみると、
\begin{equation}
{{\mathrm d\over \mathrm dx} }{\mathrm e}^{\lambda{x}}=\lambda{\mathrm e}^{\lambda{x}},~~
\left({{\mathrm d\over \mathrm dx} }\right)^2{\mathrm e}^{\lambda{x}}=\lambda^2{\mathrm e}^{\lambda{x}},\cdots,
\left({{\mathrm d\over \mathrm dx} }\right)^2{\mathrm e}^{\lambda{x}}=\lambda^n{\mathrm e}^{\lambda{x}}
\end{equation}
プリントでは上の式の右辺で$\mathrm e^{x}$のようになってましたが、$\lambda$を補って$\mathrm e^{\lambda x}$に訂正しておいてください。
となることを使うと、微分方程式は
\begin{equation}
\left(
A_n\lambda^n +A_{n-1}\lambda^{n-1}
+\cdots A_1 \lambda + A_0
\right){\mathrm e}^{\lambda{x}}=0
\end{equation}
という式に変わる。よって、
\begin{equation}
A_n\lambda^n +A_{n-1}\lambda^{n-1}+\cdots A_1 \lambda + A_0=0\label{tokusei}
\end{equation}
となるような$\lambda$が存在していれば、その$\lambda$を代入した${\mathrm e}^{\lambda {x}}$が解である。$\lambda$が満たすべき方程式と「特性方程式」と呼ぶ。
簡単な例として、特性方程式が二次になる場合をやってみよう。
\begin{equation}
\left(
\left({\mathrm d\over \mathrm dx}\right)^2
-{\mathrm d\over \mathrm dx} -2
\right)f({x})=0\label{nijiex}
\end{equation}
という微分方程式の解が${\mathrm e}^{\lambda{x}}$だと仮定し代入すると、${\mathrm d\over \mathrm dx}{\mathrm e}^{\lambda{x}}=\lambda{\mathrm e}^{\lambda{x}},\left({\mathrm d\over \mathrm dx}\right)^2{\mathrm e}^{\lambda{x}}=\lambda^2{\mathrm e}^{\lambda{x}}$を使って、
\begin{equation}
\begin{array}{rcccccl}
\biggl(&
\left({\mathrm d\over \mathrm dx}\right)^2
&
-&{\mathrm d\over \mathrm dx}&-2&
\biggr){\mathrm e}^{\lambda{x}}=0
\\
& ↓ & &↓ & & \\
\biggl(&
\lambda^2&
-&\lambda&-2&
\biggr){\mathrm e}^{\lambda{x}}=0
\end{array}
\end{equation}
という式が導かれ、特性方程式$\lambda^2-\lambda-2=0$が満たされれば${\mathrm e}^{\lambda{x}}$が解になることがわかる。特性方程式は$(\lambda-2)(\lambda+1)=0$と因数分解できるので、$\lambda=2,\lambda=-1$の二つの解があり、${\mathrm e}^{2{x}}$と${\mathrm e}^{-{x}}$が解となる。一般解は
\begin{equation}
f({x})=C{\mathrm e}^{2{x}}+D{\mathrm e}^{-{x}}
\end{equation}
ということになる。二階微分方程式は二つの未定パラメータを持つ筈なので、これで解は求まっていると考えていいだろう。
もう少し詳細に解がこれで全て求まったということを確認しておこう。二階微分方程式を解いているから、ある点${x}=x_0$での関数の値$f(x_0)$と一階微分の値$f'(x_0)$が求まれば、その後のこの関数の値はすべて求まることになる。簡単のために${x}=0$での場合を考えると、$f(0)=C+D,f'(0)=2C-D$である。$f(0),f'(0)$がどのような値でもそれに応じて$C,D$を決めてやれば、その後の関数の形は全て決まる。よってこれで一般解が求められたことになる。
ここでは特性方程式を出してから因数分解を行って$\lambda$を求めたが、もともとの微分方程式を、
\begin{equation}
\left(
{\mathrm d\over \mathrm dx} -2
\right)
\left(
{\mathrm d\over \mathrm dx} +1
\right)
f({x})=0\label{factorDE}
\end{equation}
と書き換えてもよい(いわば`微分演算子の因数分解')。この式の左辺が0になるためには、
\begin{equation}
\left(
{\mathrm d\over \mathrm dx} -2
\right)f({x})=0~~~または~~~
\left(
{\mathrm d\over \mathrm dx} +1
\right)
f({x})=0
\end{equation}
のどちらかが成り立てばよい、と考えても、$C{\mathrm e}^{2{x}}+D{\mathrm e}^{-{x}}$という解が出てくる。
さて、これで二つの解が求められた、と安心してよいかというと、一般の特性方程式$A_2\lambda^2+A_1\lambda+A_0=0$が二つの実数解を持つとは限らないので、
- $A_2\lambda^2+A_1\lambda+A_0=0$が重解を持つ場合
- $A_2\lambda^2+A_1\lambda+A_0=0$が複素数解を保つ場合
にどうするかを考えていかなくてはいけない(特性方程式が3次以上になる場合も同様である)。
特性方程式が重解を持つ場合
(2)の複素数解を持つ場合については次の\節{fukusokai}で扱うことにして、ここでは重解の場合を考えよう。
一般論を考える手がかりとして、もっとも単純な「重解になる二次方程式」である$\lambda^2=0$(解は$\lambda=0$しかない)を考えてみよう。特性方程式が$\lambda^2=0$になるような微分方程式は
\begin{equation}
\left({\mathrm d\over \mathrm dx}\right)^2 f({x})=0
\end{equation}
である。特性方程式の解は$\lambda=0$しかないから、前節の手順の通りに計算すると解として$C{\mathrm e}^0=C$という「定数解」だけが出て来る。
しかし、前節でやったことを忘れて素直に$ \left({\mathrm d\over \mathrm dx}\right)^2 f({x})=0$という式を見れば、解が
\begin{equation}
f({x})= D{x}+C
\end{equation}
なのはすぐにわかる(実際代入してみれば確かに二階微分すると0になる)。これは二つのパラメータを含んでいるから、立派な一般解である。
次に一般的に特性方程式が重解になる微分方程式として、
\begin{equation}
\left(
\left({\mathrm d\over \mathrm dx}\right)^2 -2A{\mathrm d\over \mathrm dx} +A^2
\right)f({x})=0~~~すなわち~~~
\left(
{\mathrm d\over \mathrm dx} - A
\right)^2 f({x})=0
\end{equation}
を考えてみよう。これを見て、{$ \left({\mathrm d\over \mathrm dx} - A\right) f({x})=0$}になる関数を求めればよいと考えると、$f({x})=C{\mathrm e}^{A{x}}$という解があることはすぐにわかる。しかし、解はこれで終わりではない。なぜなら我々が求めたいのは$ \left({\mathrm d\over \mathrm dx} - A\right)$を二回掛けると0になる関数なのである。よって、$ \left({\mathrm d\over \mathrm dx} - A\right)$を掛けると$(定数)\times{\mathrm e}^{A{x}}$になる関数があればそれも解なのである。
実はそうなる関数はすぐに見つかり、${x}{\mathrm e}^{A{x}}$である。確認しよう。
\begin{equation}
\left({\mathrm d\over \mathrm dx} - A\right)\left(
{x}{\mathrm e}^{A{x}}
\right)={\mathrm d\over \mathrm dx}\left({x}{\mathrm e}^{A{x}}
\right)-A{x}{\mathrm e}^{A{x}}
={\mathrm e}^{A{x}}+\underbrace{
A{x}{\mathrm e}^{A{x}}-A{x}{\mathrm e}^{A{x}}
}_{相殺}
\end{equation}
こうして、重解である場合はもう一つの解$D{x}{\mathrm e}^{A{x}}$が出ることがわかったので、
二階線型微分方程式の特性方程式が重解を持つ場合の解
\begin{equation}
\left({\mathrm d\over \mathrm dx} - A\right)^2 f({x})=0~~~の解は~~~
\left(D{x}+C\right){\mathrm e}^{A{x}}
\end{equation}
がわかる。
この答えを出す方法として、
任意の関数$F({x})$に対し、
\begin{equation}
\left({\mathrm d\over \mathrm dx}-A\right)\left(
{\mathrm e}^{A{x}}F({x})\right)
= {\mathrm e}^{A{x}}{\mathrm d\over \mathrm dx} F({x})\label{ddxA}
\end{equation}
が成り立つ。
ということを先に証明しておくというのも良い方法である(後で応用が効く)。
つまり、${\mathrm d\over \mathrm dx}-A$という微分演算子の後にあった${\mathrm e}^{A{x}}$という数を微分演算子より前に出すと、${\mathrm d\over \mathrm dx}-A$の$-A$が消えて${\mathrm d\over \mathrm dx}$になる。
\begin{equation}
\left({\mathrm d\over \mathrm dx}-A\right)\left({\mathrm e}^{A{x}}\fbox{なんとか}\right)\to {\mathrm e}^{A{x}}{\mathrm d\over \mathrm dx}\fbox{なんとか}
\end{equation}
という置き換えができるのである。この置き換えを使うと、
\begin{equation}
0= \left(
{\mathrm d\over \mathrm dx} - A
\right)^2 \left({\mathrm e}^{A{x}}F({x})\right)={\mathrm e}^{A{x}}\left({\mathrm d\over \mathrm dx}\right)^2 F({x})
\end{equation}
となるから、後は$\left({\mathrm d\over \mathrm dx}\right)^2 F({x})=0$という解き易い微分方程式を解けばよい(この答えが$D{x}+C$であることはもう知っている)。
微分の階数が高くなっても同様に
\begin{equation}
\left(
{\mathrm d\over \mathrm dx} - A
\right)^k f({x})=0~~~の解は~~~
\left(
C_{k-1}{x}^{k-1}+
C_{k-2}{x}^{k-2}+
\cdots+C_1{x}+C_0\right){\mathrm e}^{A{x}}
\end{equation}
となる(これを証明するには、実際に代入してもよいし、上で考えた置き換えを使って考えてもよい)。
以上の結果をまとめておこう。
定数係数の線型同次微分方程式
$$
\left(
A_n\left({\mathrm d\over \mathrm dx}\right)^n
+A_{n-1}\left({\mathrm d\over \mathrm dx}\right)^{n-1}
+\cdots
+A_{1}{{\mathrm d\over \mathrm dx}}
+A_0
\right){y} =0
$$
を解くには、微分演算子$\left({\mathrm d\over \mathrm dx}\right)^n$を$\lambda^n$という数に置き換えて、
$$
A_n\lambda^n
+A_{n-1}\lambda^{n-1}
+\cdots
+A_{1}\lambda
+A_0
=0
$$
という特性方程式を作る。この方程式が$n$個の相異なる解$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$を持っていたならば、
\begin{equation}
C_1{\mathrm e}^{\lambda_1{x}}
+ C_2{\mathrm e}^{\lambda_2{x}}
+ C_3{\mathrm e}^{\lambda_3{x}}
+\cdots
+ C_n{\mathrm e}^{\lambda_n{x}}
\end{equation}
が解である。解が$m$重解を含んでいた場合、重解である$\lambda_k$に対しては上の式の$C_k{\mathrm e}^{\lambda_k{x}}$を
\begin{equation}
\left(
C_{k,m-1}{x}^{m-1}
+C_{k,m-2}{x}^{m-2}
+\cdots
+C_{k,1}{x}
+C_{k,0}
\right){\mathrm e}^{\lambda_k{x}}
\end{equation}
と置き換える。
ここで「$\lambda$が複素数解を持っていた場合はどうするのか?」という点が気になる人もいるかもしれない。それについては次の節で考えよう。